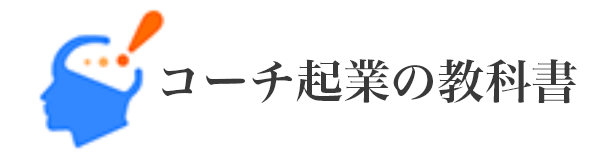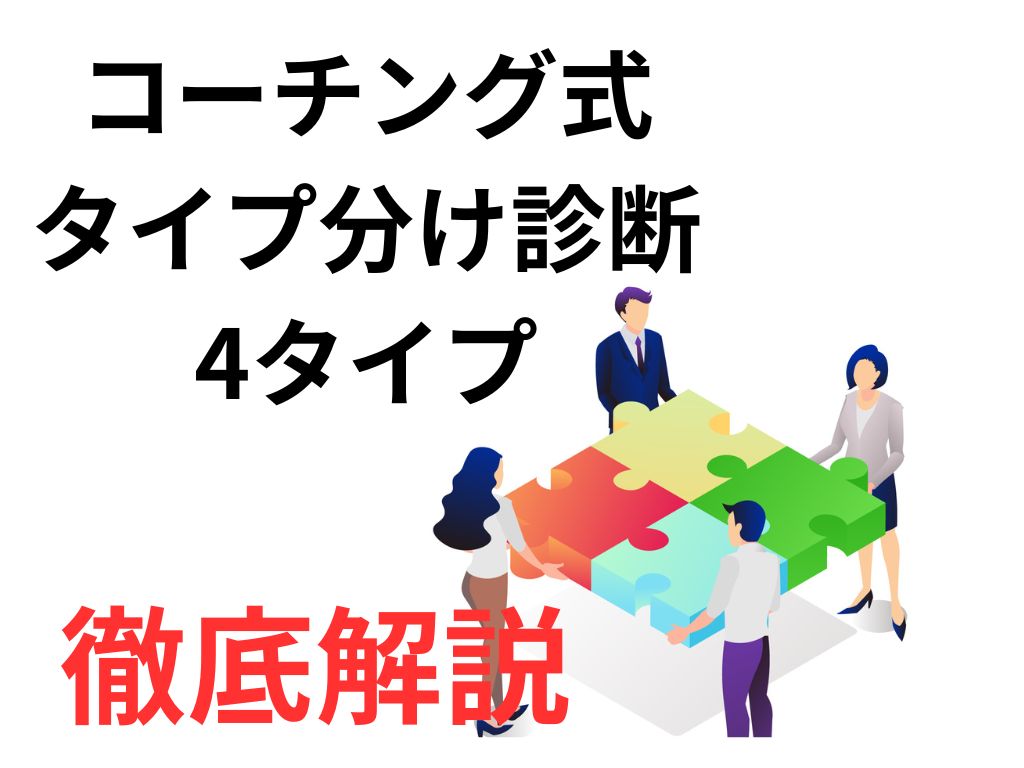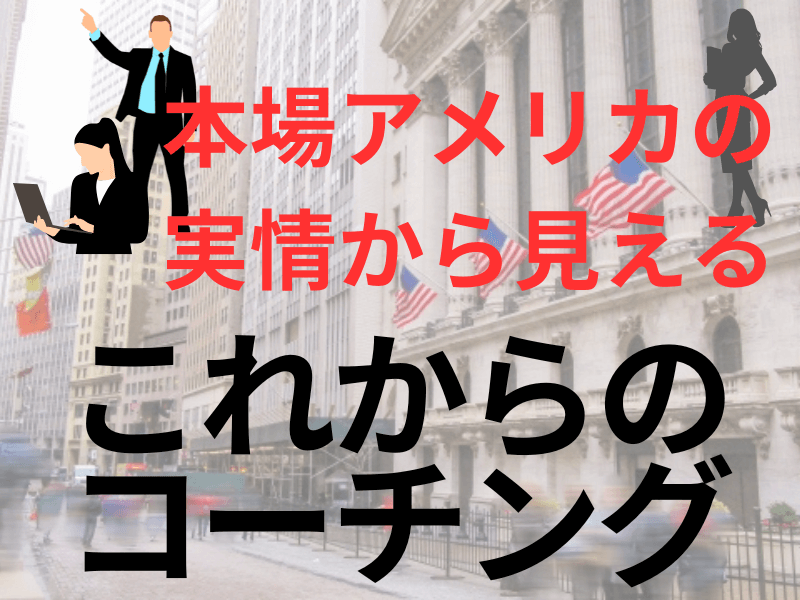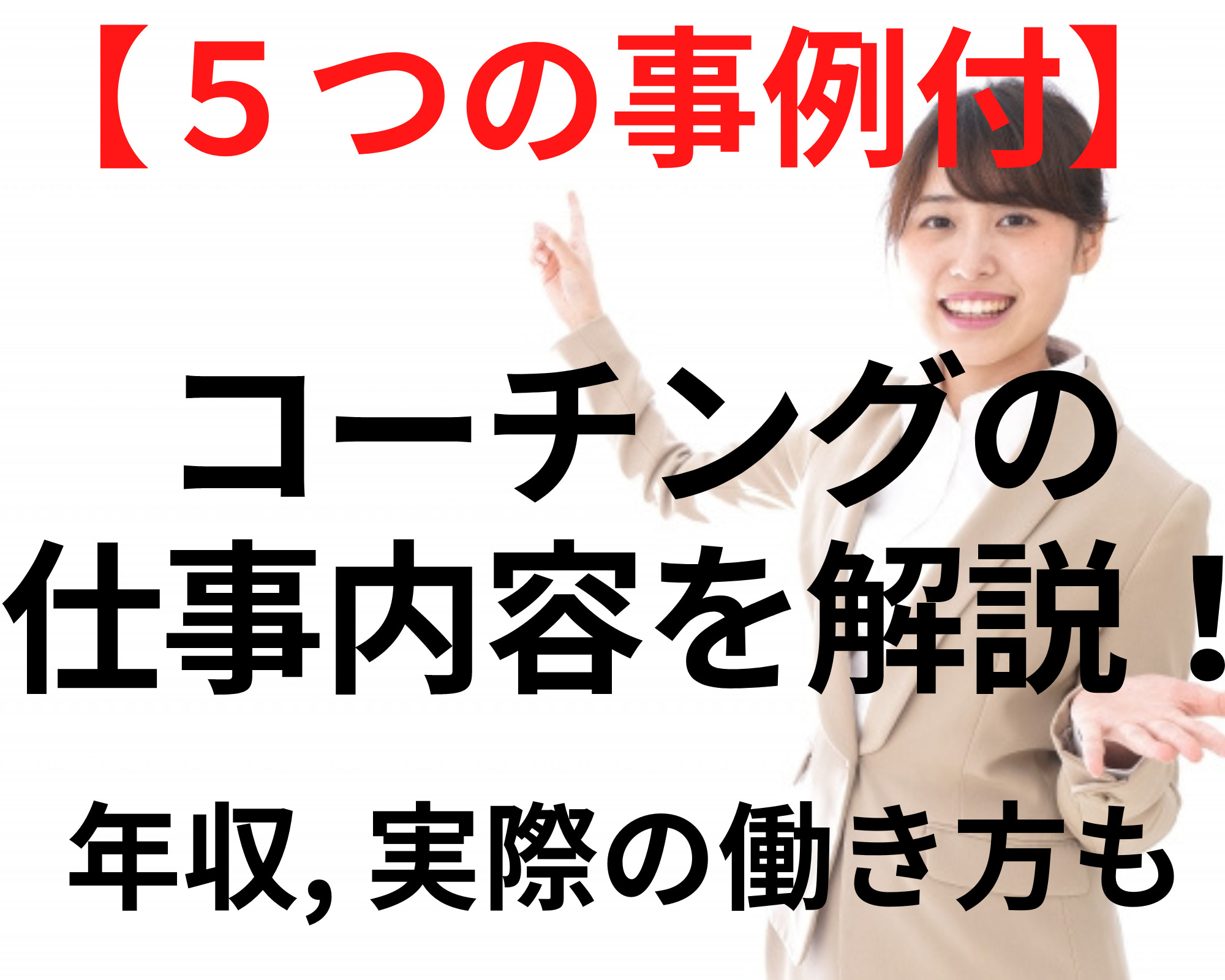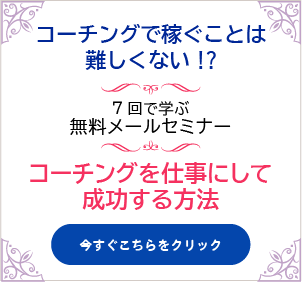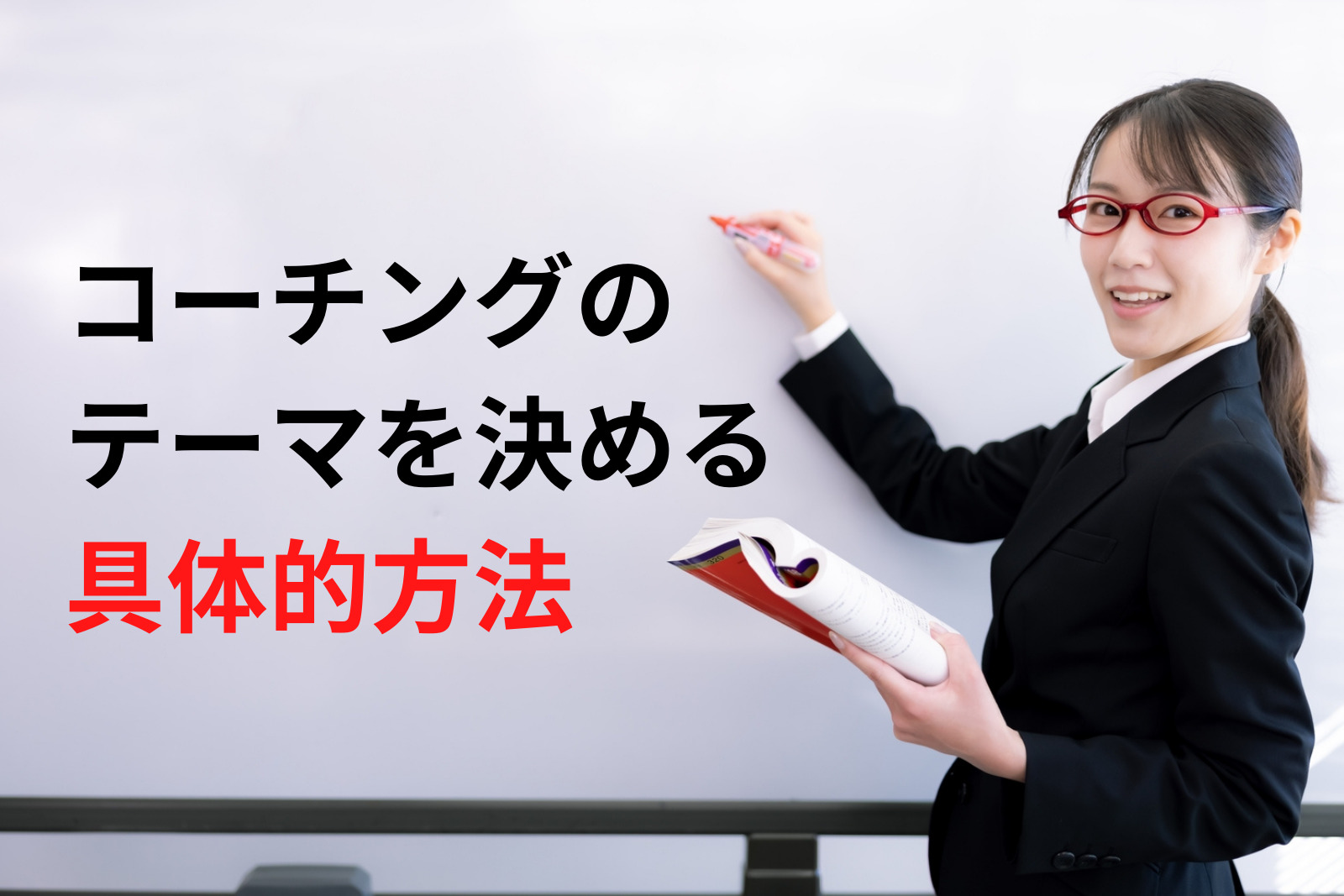コーチングの具体例│明日からすぐ使えます

「コーチングの具体例を知りたい!」
「具体的な事例をもとに勉強したい!」
こんなお悩みを抱えている方もいるでしょう。
コーチングの具体例を知るためには、全体の流れを確認しながら、実際の初回セッションの流れを確認すると効率的です。
当記事では、誰でも実践できるコーチングの流れを具体例を交えながら解説します。
目次
「コーチングとは何か?」

コーチングの流れを解説する前に、まず「コーチングとは何か?」について明確にしておきましょう。
これからプロのコーチングを受けようか考えている人も、自身がコーチとしてコーチングを実践しようと思っている人も、ぜひコーチングの原点に触れてみてください。
コーチングとは「人の成長や未来を支援するスキル」
コーチと聞くと皆さんは何を思い浮かべるでしょうか?
一般的には競技を指導するような、スポーツコーチを思い浮かべる人が多いかもしれません。
そうした指導もコーチングの1つですが、実際はそれだけにはとどまりません。
コーチングは「人の成長や未来を支援するスキル」です。
様々な分野で目指す目標や理想がある人に対して、対話をしながら気づきや行動を促し、成長をサポートします。
手取り足取り導くのではなく、あくまで「クライアントが自らの主体性を持って目標にたどりつく」ことが重要であり本質です。
そのためプロのコーチには高い対話力や洞察力などが求められます。
コーチングする分野によって仕事内容も様々です。
いくつかの例を以下の表にまとめました。
| 【コーチングの種類】 | 【仕事内容】 |
| ライフコーチ | 人間関係や仕事など生き方全般へのアプローチ |
| 恋愛・婚活コーチ | 恋愛や婚活をサポート |
| ダイエットコーチ | ダイエットをサポート |
| 子育てコーチ | 育児・子どもとの関わり方を提案 |
| セルフコーチ | 自分自身を目標達成に導く |
| メンタルコーチ | 相手の考えや気づきを引き出す |
| ビジネスコーチ | 仕事に関する課題の解決
※「企業や社員への指導」を指す場合も |
| 起業コーチ | 起業をサポートする |
| 受験コーチ | 受験勉強をサポートする |
| 英語コーチ | 英会話や英語学習をサポートする |
| スポーツコーチ | スポーツ全般を指導 |
「自分自身をコーチングする」セルフコーチングも
コーチングは人(クライアント)の成長や未来を支援するスキルと紹介しましたが、自らをコーチングするセルフコーチングという手法もあります。
自分自身の課題に対して解決策を見出し、行動に取り組んでいくことを指します。
セルフコーチングをすることで自分の目標を実現するとともに、仕事上のコーチングでクライアントの目標を達成できるようにスキルを磨くコーチもいます。
このようにコーチングは対象も分野も様々な技術です。
より詳しくコーチングの種類や資格について知りたい場合は、以下の記事を見てみると良いでしょう。
コーチングの具体例1.全体の流れを確認する
 コーチングのセッションを知るためには、全体の流れを一度ざっくりと確認してみましょう。
コーチングのセッションを知るためには、全体の流れを一度ざっくりと確認してみましょう。
- クライアントと契約する
- クライアントの目標を決める
- 次回セッションの予定を決める
- 目標が達成できているかを確認する
このような流れで毎回のコーチングが進んでいくのが基本です。
もちろん、この中にクライアントが抱えている悩みを一緒に解決したり、課題解決をコーチ自身が行ったりすることもあるでしょう。
より詳しくセッションの流れを知りたい方は次の記事を参考にしてみてください。
コーチングの具体例2.コーチングとティーチングの違いを知る
 セッション全体の流れを確認したところで、セッションをスタートする前にコーチングとティーチングの違いを知っておきましょう。
セッション全体の流れを確認したところで、セッションをスタートする前にコーチングとティーチングの違いを知っておきましょう。
というのも、コーチとなったからには、コーチングすべきところとティーチングすべきところを明確に分ける必要があるからです。
簡単にコーチングすべきところとティーチングすべきところを区分しておくと、次のとおりです。
- コーチング:クライアント自身の心が重要な箇所
- ティーチング:コーチがクライアントの課題解決をする箇所
それぞれを確認していきましょう。
コーチングは答えをクライアントが出す
 コーチングとは「相手の心の中にある答えを引き出す」という前提で、対話を行っていくものです。
コーチングとは「相手の心の中にある答えを引き出す」という前提で、対話を行っていくものです。
答えを誘導するのではなく、クライアントが何を考え・どう生きていきたいかなどの抽象的な考えから、期限を決めて何をするのかといった具体的な目標設定も引き出します。
たとえば、「あなたはこれからどうしたらいいですか?」とオープンクエスチョンを投げかけ、さまざまな考えを引き出すのがコーチングの手法です。
このようにコーチングは答えが決まっていなかったり、自分自身が目標を決めなければならなかったりするときに役立つ手法といえるでしょう。
コーチングのメリットとデメリットを知る
コーチングというと理想的な指導手法のように聞こえますが、もちろんメリット・デメリットが存在する点にも注意しましょう。
コーチングのメリット
コーチングのメリットをまとめると次のとおりです。
- クライアントが本当に求めていることを知れる
- 内発的動機につながるため、モチベーションが持続しやすい
- クライアントに自走力が身につく
コーチングはクライアントが本当に求めていることを深堀りして知っていく手法なので、濃密なコミュニケーションが取れます。
また「10万円あげるから頑張ろう」といった外発的動機付けとは違い、コーチングは「自分の本当にしたいことはなんだろう…」と内発的動機付けを行うためモチベーションが持続しやすいのが特徴です。
これらのメリットをまとめると総じて「自走力(自分で考え動く力)」がコーチングを通してクライアントに身についていきます。
コーチングのデメリット
逆にコーチングのデメリットは次のとおりです。
- コーチングする側にスキルがないと価値を発揮できない
- クライアントによっては成果が出るまでに時間がかかる
コーチングは人の心に寄り添う形でセッションを行っていくので、コーチ側には非常に高い人間力やスキルが必要とされます。
人間力やスキルと一口にいっても、信頼される力や安心させる力、そもそものコーチングスキルなどの人間としての総合力が試されるものだと考えておきましょう。
またクライアントによっては、自分自身の胸の内をきちんと考えたことがなく、なかなかさらけ出せない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、自分の胸の内をさらけ出せないのに、すぐに成果を出したいというニーズがあると、途中で契約が打ち切られてしまうこともあるので、コーチは時間と成果に常に追われてしまう可能性があります。
ティーチングは答えを先生が出す
 ティーチングはティーチャーという言葉があるように、人に物事を正確に教える手法です。
ティーチングはティーチャーという言葉があるように、人に物事を正確に教える手法です。
1対1やその他複数のクライアントに対して教授を行います。
ティーチングをするとクライアントの課題に対してスピーディーに答えや成果を出せるようになります。
コーチングと違い対話は基本的に行われず、一方通行となりやすいのが特徴です。
ティーチングのメリットとデメリットを知る
コーチングと同様に、ティーチングのメリットとデメリットを確認していきましょう。
ティーチングのメリット
ティーチングのメリットをまとめると次のとおりです。
- クライアントが望む答えを提示できる
- 素早く結果を出せる
- 信頼獲得につながる
ある特定分野に突出した知識や経験を持っていると、クライアントが望む答えを直接提示したり、素早く結果につながる指導を行えたりします。
これはそのままコーチの信頼につながり、その後のリピート契約にもスムーズに進むようになるでしょう。
ティーチングのデメリット
逆にティーチングのデメリットは次のとおりです。
- クライアントが指示待ちになりがち
- 一方的な指導になるのでモチベーションが下がりやすい
- 素早い結果を残せないとその後の指導が難航する
ティーチングは一方通行のコミュニケーションになりがちなので、クライアントが指示待ちになってしまったり、ある意味強制的に知識を教えることになるので、モチベーションが持続しなかったりします。
また、コーチ側にスキルがないとクライアント側は不審に思い、リピートにつながらなかったり、成果が出なかったりします。
こうなると今後も成果を出せずに契約が打ち切られてしまうので注意が必要です。
コーチング中にもティーチングは行ってもいい
ここまでコーチングとティーチングの違いをお伝えしてきましたが、コーチングを行おうとする方は、ティーチングを行ってはいけないと勘違いしがちです。
「コーチングをしているんだから、コーチングだけで成果を出してあげなくちゃ」というような思い込みがあると、クライアント側のニーズと合致せずに契約が途中終了することもあります。
ですから、考え方を変えて、適切なタイミングでコーチングとティーチングを使い分けていきましょう。
たとえば、最初にティーチングを行って圧倒的な成果をクライアント側が出し、その後コーチングを行うといった導線であれば、そもそも信頼がある上でコーチングができるので、さらに成果を出しやすくなるはずです。
そのほか、コーチングと混同されやすい言葉やその違いについて知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
コーチングとカウンセリング・心理学・セラピーなどは何が違うか知る
ここからは、どのようにティーチングとコーチングを切り替えるのかを解説していきます。
コーチングの具体例3.ケーススタディ
 それではケーススタディとして、ティーチングを行ったほうがいい事例とコーチングを行ったほうがいい事例を確認していきましょう。
それではケーススタディとして、ティーチングを行ったほうがいい事例とコーチングを行ったほうがいい事例を確認していきましょう。
ティーチングを行ったほうがいい事例
ティーチングを行ったほうがいい事例は、クライアントが明確な課題を持っているときです。
具体的にはダイエットや減量を行うコーチングの事例を想定してみましょう。
クライアント「8月までに水着を着てもボディラインが綺麗に見えるようにしたいんです!」
このように初回セッションで明確な課題をクライアント側から提示されたとしましょう。
- コーチA「では、痩せるとどんな自分になっていますか?」
- コーチB「では、まず食事内容と運動量を聞きながら、適切なダイエット法を教えますね」
この両者だとクライアントはどちらを選ぶでしょうか?
明確な課題意識を持っているクライアントであれば、コーチBを選びますよね。
となると、この場合には「教える」といった言葉を使っているティーチングが適切な方法であることがうかがえます。
コーチングを行ったほうがいい事例
同様にしてコーチングを行ったほうがいい事例を考えてみましょう。
クライアント「ただ綺麗になりたいという思いはあるんですが、ダイエットするモチベーションが湧きません」
このように初回セッションでモチベーションに関する質問をされたとしましょう。
- コーチA「では、痩せるとどんな自分になっていますか?」
- コーチB「では、まず食事内容と運動量を聞きながら、適切なダイエット法を教えますね」
先ほどと同様の質問をしていますが、クライアントからの質問について明確に解決に導こうとしているのは、コーチAとなりました。
このようにクライアント自身が「どうなりたいか」や「どうしたいか」を悩んでいるときにはコーチング技術を使うのが適切です。
コーチングの具体例4.GROWモデルから見るコーチングの流れ
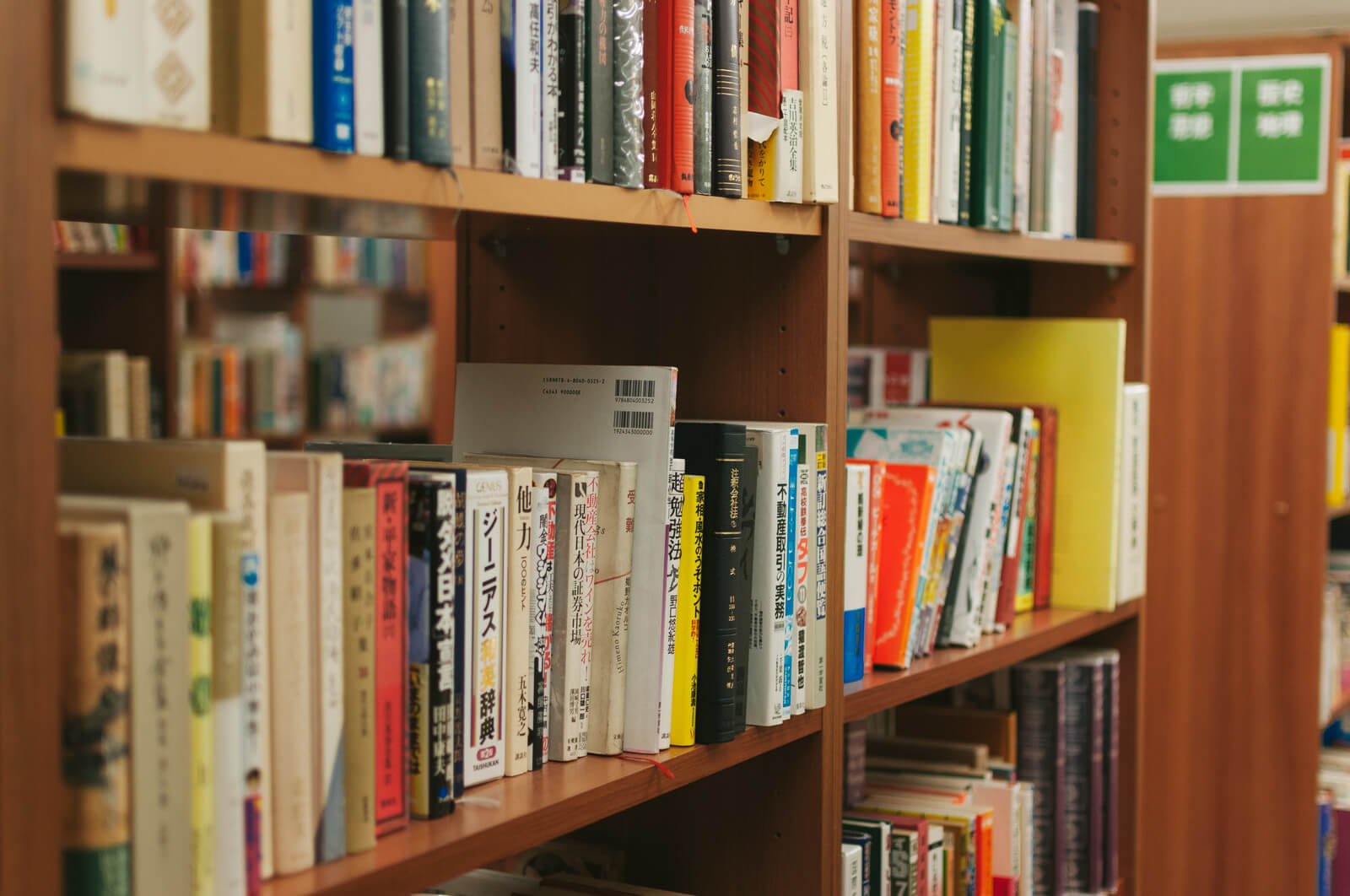
ここまでコーチングとティーチングの違いに触れ、適切な使い分けについて解説してきました。
この項目ではコーチングの基本プロセスの1つ「GROWモデル」を紹介し、クライアントの「こうなりたい」「こうしたい」を実現していく流れの一例として紹介します。
GROWモデルとは何か
GROWモデルはビジネスコーチングの権威、ジョン・ウィットモア氏が確立したコーチングモデルです。
- Goal:目標の明確化
- Reality/Resource:現状の把握と資源の発見
- Options:選択肢の創造
- Will:行動計画と目標達成の意思
この4つの頭文字をとって名づけられました。
ゴールを設定し、どう達成していくかをクライアントと共に具体化していくプロセスを解説したものです。
このモデルに従って、実際にどうコーチングを展開していくか見ていきましょう。
G:クライアントを深く知り「テーマと目的を明確にする」
まずはクライアントを深く知り、ゴールとなる「テーマと目的」を明確にします。
「こうなりたい」「こうしたい」を明確に形にし認識してもらうことで、その後の行動選択やプロセスを引き出しやすくなり、モチベーションの持続に繋がります。
生き方や価値観が違えば目指すゴールも大きく変わるので、クライアントを深く知るための質問を投げかけていきましょう。
- あなたは人生の何を変えたいですか?
- 人との関係において何を重要視していますか?
- 〇ヶ月後に何が達成できていたら嬉しいですか?
- なぜそれを達成しようと思うのですか?
テーマ設定の方法や具体例をより詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。
R:「現状の把握」と「資源の発見」をする
テーマと目的が設定出来たら、次は「現状の把握」と「資源の発見」の段階です。
ゴールと現実のギャップを確認して「どうすればゴールに近づけるか」を明確にすると同時に、クライアントがこれまでやってきたことを引き出して、使える資源(人・物・資金・情報など)として提示します。
例えば今回は「豊かな老後を送る」をテーマに、そのために「年間に100万貯める」を1つの目的に設定したとしましょう。
以下のような質問で必要な情報をさらに引き出します。
- 今、何が問題だと感じていますか?
- このままの状態が続くと、あなたや周りにどんな影響が出るでしょうか?
- 老後資金やライフプランに詳しい人は周りにいますか?
- 目標達成のために活かせそうなあなたの強みや経験は何でしょうか?
O:「選択肢の創造」で様々な行動パターンを想定してもらう
この段階では、目的をかなえるための行動目標を自由な発想で考えてもらいます。
そのためになるべく多くの選択肢を考え検討していきます。
「もし」を使ったスライドアウトの質問を使って思考の制限を外してあげると、視点を切り替えることができるのでおすすめですよ。
ブレインストーミングである程度選択肢を出し切ってもらったら、その中からベストなものを絞っていきましょう。
- もし何でもできるとしたらどんな行動をとりますか?
- これまで試したことのない実践や方法はありますか?
- 明日からでも出来ることは何でしょうか?
- あなたが一番本気で取り組みたいものはどれですか?
W:「行動目標と達成の意思を確認」する
最後はテーマと目的を達成するための行動目標(手段)を設定していきます。
いつ・どこで・どれだけ・何をするのかを明確に決めることがポイントです。
選択肢や行動パターンを出すだけでは具体的なアクションに繋がらないので、プランを作成して達成に対する責任を持ってもらいましょう。
以下のような質問で具体的な行動計画にしていきます。
- 具体的に何をしていきますか?
- まず何から取りかかりますか?
- 今月末までにどこまで達成できますか?
- いつまでに何を達成しますか?
こうしてテーマ・目的・行動計画(手段)を明確にする流れを繰り返していきます。
| テーマ | 豊かな老後を送る |
| 目的 | 年間に100万貯める |
| 行動目標
(手段) |
①電気代を5000円安くする
②1日500円貯金をする ③趣味に使うお金を月々10,000円節約する : |
コーチングの目標設定については以下の記事でも取り上げていますので、参考にしてみてください。
コーチングの具体例5.初回セッションのロープレ
 ここまでコーチングとティーチングのケーススタディやGROWモデルから見たコーチング全体像の把握を行ってきましたが、次は実際に初回セッションを行うときのロープレを行ってみましょう。
ここまでコーチングとティーチングのケーススタディやGROWモデルから見たコーチング全体像の把握を行ってきましたが、次は実際に初回セッションを行うときのロープレを行ってみましょう。
具体的には次のような流れで初回セッションは行われます。
- クライアントと契約する
- テーマを決める
- 数値目標を立てる
- 次回の予定を決める
それぞれ解説していきます。
クライアントと契約する
初回セッションもしくは初回セッション前には必ずクライアントと契約を行わなければなりません。
というのも、コーチングは無形のサービス提供となるので、クライアント側が「コーチングを受けていない」と主張し、あなたがサービス提供の証拠を出せなければ契約金額を払い戻す必要があるからです。
また、契約時にはクライアント側からの信用を得るために、細かいところまですぐに答えられるように問答集を作っておくといいでしょう。
テーマを決める
クライアントとの契約が明確に締結されたら、続いてはテーマを決めていきます。
テーマとは、数日から数ヶ月、場合によっては1年を掛けて取り組むコーチングの方向性を決めるものです。
たとえば、経営コーチングであれば新規事業のためのコーチングであったり、恋愛コーチングであれば本当に好きな人を見つけるコーチングであったりと抽象的(ふんわりしたもの)でありながらも、全体の方向性を示す言葉をクライアントとともに見つけていきます。
テーマ決めはふんわりした概念(考えや思い)を取り扱うため、ある程度のテクニックが必要です。
その点に関して詳しくまとめた記事があるので、気になる方は参考にしてみてください。
※この時点で先ほどお伝えした、課題解決のためのティーチングを挟む必要があれば行うようにしてください。
数値目標を立てる
テーマが決まったら数日から数ヶ月の長期間にわたって行うコーチングの目的と数値目標を決めていきましょう。
テーマを全体の方向性とするなら、中長期的な目標が「目的」、目的を達成するための手段を具体化したものが「数値目標」と捉えてください。
たとえばケーススタディで提示したダイエットコーチの場合、テーマ、目的・数値目標は次のように分かれます。
- テーマ:ダイエットをして綺麗になる
- 目的:8月までに健康的に減量する
- 数値目標:4月までに1kg減量する
このように大きな考えから小さなステップに焦点をあてていきます。
数値目標が立てられたのなら、その数値を達成するために毎日行うことを決めていきます。
この数値目標に関してはコーチなら誰でも使えるワークシートを用意しているので、以下の記事を確認してみてください。
次回の予定を決める
数値目標まで立てられたら初回のコーチングセッションはほぼ終わりです。
しかし、ここでセッション全体が終了したと気を緩めてはいけません。
次回のセッション予定を組みながら、セッション後のフォローも行います。
というのも、人は行動をすぐに変えられないので、初期の頃は徹底したチェック体制が必要だからです。
たとえば、クライアントの数値目標の進捗をチャットツールを使って確認するといいでしょう。
このように密なコミュニケーションが取れると、クライアントもコーチングで決めた目標数値を達成しやすいはずです。
コーチングの具体例6.会話例を確認してみよう

様々な観点から具体例をお伝えしてきましたが、ここからはクライアントとの実際のやりとりについて、会話例を紹介していきます。
コーチングするうえでポイントになるのが、以下の3つのコミュニケーションスキルです。
それぞれ見ていきましょう。
- 傾聴(聴く)力
- 承認力
- 質問力
「傾聴(聴く)力」を活かす会話例
コーチングにおける傾聴(聴く)力とは、クライアントの話をただ漠然と聞くだけではなく、問題解決や目標達成のためにクライアントの問題を整理し認識させるために必要なスキルです。
クライアントが抱える問題は「表面的・顕在的なもの」と「深層的・潜在的なもの」があります。
会話の中では「聴く」ことに加えて表情や声のトーン・動作といったクライアントの全てに集中することで、それを読み取り理解することが求められます。
そのため積極的・自発的な会話より、以下のようなやりとりで聴くことに徹してみましょう。
うなずいたりあいづちを打つ
相手の会話に集中するためにあえて沈黙することも必要ですが、クライアントに聴いている姿勢を示し安心感を与えるために、少し大げさにうなずいたり適度にあいづちを打ちましょう。
- なるほど!
- そうかもしれませんね
- それからどうなりましたか?
オウム返しをする
オウム返しをすることでクライアントへの共感を示すことができます。
相手の感情を勝手に解釈したり、言い換えたりしないように注意しましょう。
クライアント「〇〇ということがあって、すごくモヤモヤしてしまって」
コーチ「なるほど、モヤモヤしてしまったんですね」
「承認力」を活かす会話例
コーチングにおける「承認」とは、目標に対しての成果とクライアントのどんな小さな変化や成長にも気づき、それを伝えることを指します。
クライアントは承認されることで安心感が得られ、自己肯定感やモチベーションが高まります。
相手の成長や変化を具体的に、なるべく早く伝えてあげましょう。
- この前まで1時間かかっていた作業が、最近は30分で出来るようになりましたね
- 〇〇さんは英語のスキルを高めるために毎日何時間も勉強していましたよね
「質問力」を活かす会話例
クライアントの目標達成への方向性を左右する重要なスキルが「質問力」です。
コーチングにおける「質問」とは、クライアントの深層にある本音を引き出したり、目標設定や行動を促したりするためのものです。
「自分が望む答え」ではなく、「相手(クライアント)が望む答え」を引き出すための質問であることを理解しておきましょう。
- あなたが今、一番変えたいと思っていることは何ですか?
- それが達成できたら何が可能になるでしょう?
- いつまでに何をしましょうか?
クライアントが発した言葉から、その背景を考えるための質問も大切です。
クライアント「仕事って本当に難しいですね…」
コーチ「今、何か仕事で悩んでいることがあるのですか?」
コーチングの質問については以下の記事でさらに詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
コーチングはクライアントがいないとスタートしない
 ここまでコーチングの具体例を詳しくお伝えしてきましたが、そもそもコーチングを実践しようと考えても最初のクライアントがいなければ、セッションはスタートしません。
ここまでコーチングの具体例を詳しくお伝えしてきましたが、そもそもコーチングを実践しようと考えても最初のクライアントがいなければ、セッションはスタートしません。
それに加えて、コーチングは実績のある方に依頼が集中しがちなので、いかに早く実績を積んでいけるかがとても大切です。
ですから今回の記事でお伝えした具体例を知ったらすぐにクライアント探しをしていきましょう。
この集客方法はメルマガを通してお伝えしているので、気になる方は次の記事を見てみてください。